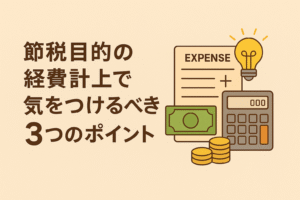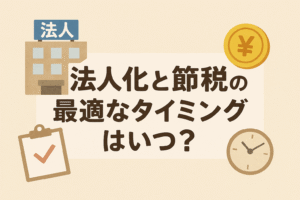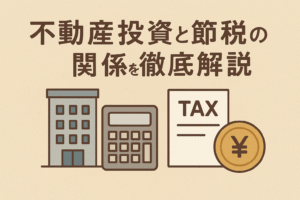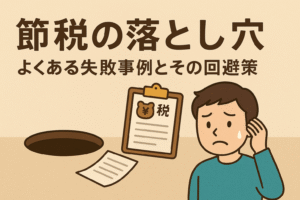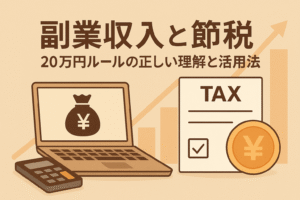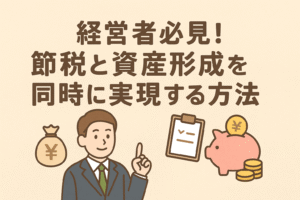赤字でも節税は可能なのか
会社や事業が赤字の場合、「節税」という言葉はあまり意識されないかもしれません。
しかし実際には、赤字でも適切な会計・税務処理を行うことで、将来の税負担を減らす「節税効果」を生み出せます。
その代表的な手段が繰越欠損金と減価償却です。
これらは現金支出を伴わずに損金を計上できたり、赤字を翌期以降の黒字と相殺できたりするため、長期的に見て税額を抑え、キャッシュフローを改善する効果があります。
赤字時にこそ意識すべき理由
赤字の年度は法人税や所得税の納付は発生しません。
しかし、赤字額や資産の会計処理方法を適切に記録・申告しておくことで、翌年度以降の黒字転換時に税金を減らすことができます。
特に中小企業や個人事業主の場合、景気や取引状況の変動で黒字と赤字が交互に訪れることは珍しくありません。
そのため、赤字の年にどのような会計処理を選択するかが、将来の節税額を大きく左右します。
繰越欠損金とは何か
繰越欠損金とは、赤字(欠損金)を翌年度以降の黒字と相殺できる制度です。
税務上の所得計算では、当期の赤字額を将来の利益から差し引くことが可能で、結果として納税額を減らせます。
繰越期間
- 中小企業や個人事業主:最大10年間繰り越し可能
- 大企業:同じく10年だが、一部制限あり(控除限度あり)
控除限度
- 中小企業等の場合:制限なし(黒字額全額と相殺可能)
- 大企業の場合:所得の50%まで控除可能
減価償却とは何か
減価償却とは、固定資産を購入した際、その費用を購入年度に全額経費計上するのではなく、耐用年数に応じて少しずつ費用化していく方法です。
これにより、資産を使う期間に応じて費用を配分し、利益の平準化や税額調整が可能になります。
現金支出を伴わない費用計上
減価償却費は、購入年度以降は現金支出を伴わずに経費として計上できるため、黒字年度の節税効果が高まります。
赤字年度にも計上可能で、翌期以降の繰越欠損金と合わせることで、長期的な節税戦略に活用できます。
赤字時に減価償却を計上するべきか
赤字の年度にあえて減価償却を進めるか、繰り延べるかはケースバイケースです。
- 計上する場合のメリット
翌期以降の繰越欠損金を増やせるため、黒字転換時の節税額が大きくなる。 - 計上しない場合のメリット
将来の黒字年度に減価償却費を残せるため、その時の節税効果を確保できる。
この判断は、将来の利益見込みや設備更新計画を踏まえて行うことが重要です。
繰越欠損金と減価償却を組み合わせた節税効果
赤字の年度において、繰越欠損金と減価償却を上手く活用することで、将来の税額を大きく減らせます。
組み合わせのポイント
- 赤字年度に減価償却をしっかり計上
→ 繰越欠損金を増やし、翌期以降の黒字と相殺。 - 黒字年度に減価償却を温存
→ 赤字年度はあえて一部減価償却を行わず、黒字年度に経費化する。
この2つの戦略は相反するように見えますが、将来の利益予測に応じて柔軟に選択することが重要です。
繰越欠損金の活用例
ケース1:赤字から黒字へのV字回復
- 2023年度:▲500万円の赤字(欠損金500万円)
- 2024年度:利益800万円
- 繰越欠損金を全額利用 → 課税所得は300万円に減少
節税効果
法人税等を約30%と仮定すると、500万円×30%=150万円の税額削減。
減価償却の活用例
ケース2:大型設備投資の減価償却
- 2023年度:機械装置を2,000万円で購入(耐用年数10年)
- 定額法:年間200万円を費用化
- 2023年度が赤字であっても200万円を経費計上可能 → 繰越欠損金が増える
翌年度の黒字と相殺でき、結果的にキャッシュアウトを減らせる。
節税とキャッシュフローの関係性
赤字でも節税が可能な理由は、税務上の利益計算と実際の現金の動き(キャッシュフロー)が異なるためです。
キャッシュフローにプラスの影響
- 繰越欠損金:翌期以降の税額を減らすことで現金流出を抑える
- 減価償却:現金支出なしで経費を増やし、課税所得を減らす
結果として、手元資金を温存し、事業投資や運転資金に回すことが可能になります。
制度活用時の注意点
- 申告漏れに注意
繰越欠損金は申告書への明記が必須。漏れると権利を失います。 - 減価償却方法の選択
定額法・定率法の選択は慎重に。将来の利益見通しを考慮。 - 繰越期間の管理
10年間の期限内に使い切らなければ効果がなくなる。
実務での流れ
- 赤字年度の損益計算書を確定
- 減価償却費の計上有無を判断
- 繰越欠損金額を確定し、別表に記載
- 翌期以降、黒字年度で控除適用
実行のためのアクションプラン
- 将来の利益予測を立てる
売上・利益計画を3〜5年スパンでシミュレーション。 - 減価償却スケジュールを決定
設備投資予定と利益見込みをリンクさせる。 - 税務申告の正確性を確保
税理士や会計ソフトでミス防止。 - 毎年の繰越欠損金残高を把握
年度ごとの明細を管理し、期限切れを防ぐ。
まとめ
赤字の年度であっても、繰越欠損金と減価償却を適切に活用することで、将来の黒字年度の税負担を大幅に減らすことが可能です。
これらは現金支出を伴わない、もしくは過去の支出を活かす節税手段であるため、キャッシュフローを維持しながら税額を減らせるという特徴があります。
- 繰越欠損金は最大10年間利用でき、中小企業であれば黒字全額と相殺可能
- 減価償却は資産を持つ限り毎年経費化でき、利益圧縮に有効
- 両者を組み合わせることで長期的な税負担軽減と資金繰りの安定化が実現可能
長期的な税務戦略の提案
- 利益予測と繰越欠損金の活用計画をセットで管理
黒字見込みの年度に合わせて欠損金を最大限使えるよう調整。 - 設備投資と減価償却を戦略的に計画
資金繰りに余裕がある年度に投資し、減価償却を黒字年度に集中させる。 - 毎期の税務申告で記録を正確に残す
欠損金の申告漏れや償却漏れは致命的な損失につながるため、必ず申告書のチェックを徹底。 - 税制改正情報をウォッチ
繰越期間や控除限度、償却方法の改正があれば、即座にシミュレーションを見直す。
実務上の注意点
- 繰越欠損金は必ず税務申告書に記載(別表七など)
→ 記載漏れはその年分の欠損金控除不可 - 減価償却の償却漏れは過年度に遡って修正できないケースあり
→ 固定資産台帳と決算書の一致を必ず確認 - 設備投資時は補助金や特別償却制度との併用を検討
→ キャッシュアウトを減らしつつ節税効果を拡大
行動ステップ(チェックリスト)
- 今期の赤字額と繰越欠損金残高を確認
- 翌期以降3年間の利益予測を作成
- 設備投資計画と減価償却の見込み額を整理
- 税理士と繰越欠損金の消化スケジュールを共有
- 毎期末に繰越欠損金・償却状況を再確認
結論
赤字は単なるマイナスではなく、将来の節税の種になります。
繰越欠損金と減価償却は、適切に管理すれば長期的な資金繰り改善と税負担軽減を両立できる強力なツールです。
経営計画と税務計画を一体で考えることが、安定した企業運営への近道となります。