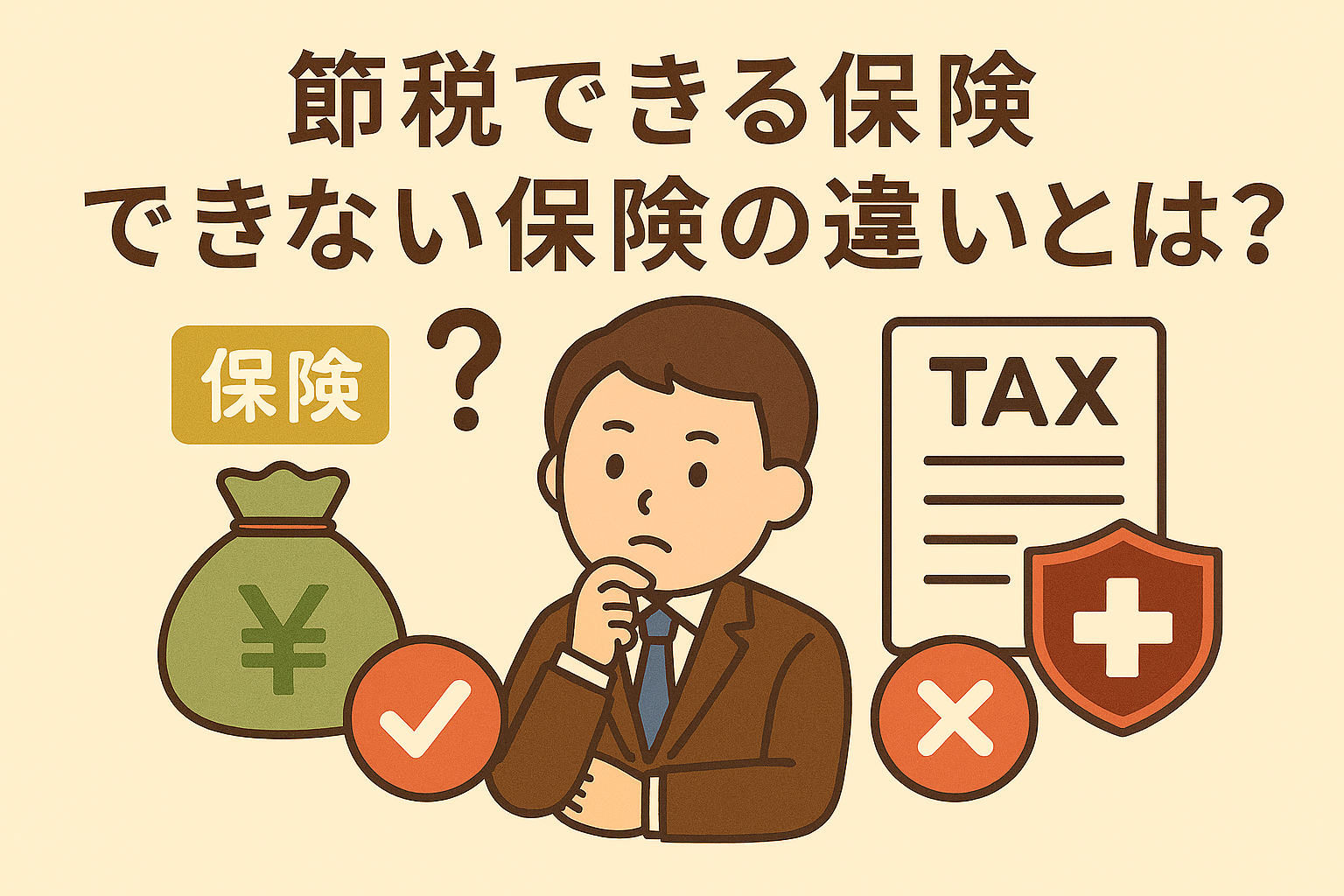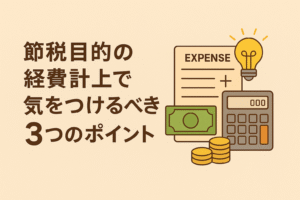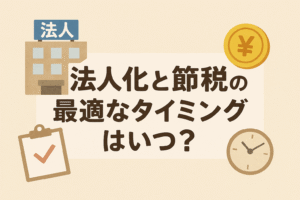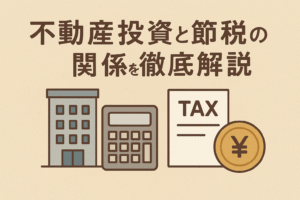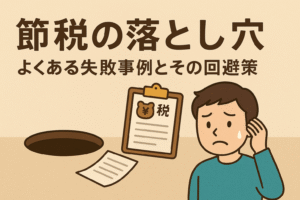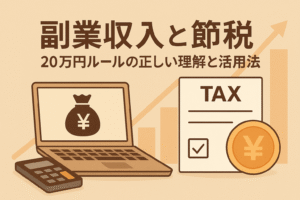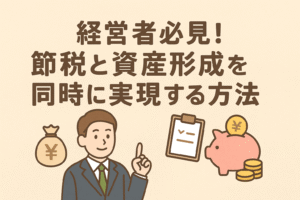節税になる保険とならない保険、その境界線とは?
企業や個人事業主にとって、保険は単なるリスク対策だけでなく、節税の手段としても利用されるケースがあります。
しかし、すべての保険が節税になるわけではなく、契約内容や税務上の取扱いによっては全く節税効果がないどころか、将来の税負担が増える場合もあります。
この記事では、法人保険や個人事業主向け保険を中心に、節税になる保険とならない保険の違いを分かりやすく解説します。さらに、2025年時点での税制ルールを踏まえ、具体的な選び方や注意点を紹介します。
保険が節税になる条件とは?
節税になるかどうかは、税務上「保険料が損金(経費)として認められるか」にかかっています。
法人税法や所得税法では、事業に関連する支出であること、そして契約内容が税務上の要件を満たすことが必要です。
節税になる保険の代表例は以下の通りです。
- 法人向け定期保険の一部(一定条件の死亡保障型)
- 経営セーフティ共済に付随する保険契約
- 損害保険(火災保険、賠償責任保険など事業資産に関するもの)
一方で、節税にならない保険の多くは「私的保障」「貯蓄性が高い契約」「事業関連性が薄い契約」です。
節税にならない保険に手を出すと起こる問題
節税目的で保険に加入したつもりでも、実は損金にならず、結果的に税負担が変わらないことがあります。
さらに、解約時や満期時に受け取る保険金が一時的に益金として課税され、トータルで見ると節税効果がマイナスになることもあります。
典型的なリスクは次の通りです。
- 税務調査で経費否認される
- 保険解約時に一時的な高額益金が発生し、税率の高い年度に課税される
- キャッシュフローが固定化され、必要な時に資金を動かせない
節税になる保険とならない保険の分類表
| 保険の種類 | 節税になるか | 損金算入可否 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 定期保険(一定条件) | 〇 | 全額または一部損金 | 死亡保障が主目的で貯蓄性が低い |
| 経営セーフティ共済関連 | 〇 | 全額損金 | 掛金全額が損金、保険部分は事業関連性あり |
| 火災・損害保険 | 〇 | 全額損金 | 事業資産や事務所を対象 |
| 長期平準定期保険(改正後) | △ | 一部損金 | 解約返戻率や契約年数による制限あり |
| 終身保険 | × | 損金不可 | 貯蓄性が高く私的保障色が強い |
| 個人向け医療保険(法人契約) | × | 原則損金不可 | 従業員福利厚生に該当すれば一部可 |
なぜ保険によって節税効果が違うのか
保険が節税になるかどうかは、契約の目的・保障内容・解約返戻金の有無などによって変わります。
税務上の基本的な考え方は次の通りです。
1. 事業関連性の有無
保険の目的が事業活動に直接関係していれば損金算入されやすくなります。
例:事務所の火災保険、役員の事業保障目的の定期保険。
2. 貯蓄性(解約返戻金)の有無
貯蓄性が高い保険は「将来の資産形成」が主目的とみなされ、資産計上となり損金になりにくい傾向があります。
3. 税制改正の影響
過去には全額損金扱いだった法人保険も、解約返戻率や契約年数によって制限されるようになりました。特に2019年以降、法人向け保険の損金算入ルールは厳格化されています。
具体例で見る節税になる保険・ならない保険の判断基準
節税になる保険の事例
法人向け定期保険(一定条件の死亡保障型)
- 契約形態:法人が契約者・保険料負担者、役員や従業員が被保険者
- 損金算入:保険料の全額または一部
- 活用例:代表者に万一があった場合の事業継続資金確保
→ 貯蓄性がなく、死亡保障のみであれば全額損金となり、即時の節税効果あり。
火災・賠償責任保険
- 契約形態:事業用資産(工場・店舗・事務所)を対象
- 損金算入:全額損金
- 活用例:店舗火災や顧客への賠償リスク対策
→ 保険料全額を経費にでき、実質的な節税とリスク管理を同時に実現。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
- 契約形態:法人または個人事業主が契約者
- 損金算入:掛金全額
- 活用例:取引先倒産による連鎖倒産リスク回避
→ 掛金は全額損金で、解約時に資金を戻すことが可能。
節税にならない保険の事例
終身保険
- 契約形態:法人が契約者であっても、解約返戻金が高額
- 損金算入:不可(資産計上)
- 問題点:将来の退職金準備目的で使われることが多いが、税務上は貯蓄扱い。
個人向け医療保険(役員用)
- 契約形態:法人契約だが、保障が私的医療費補填のみ
- 損金算入:原則不可(福利厚生規程で全社員対象の場合は可)
- 問題点:役員個人の保障目的と見なされれば経費否認リスクあり。
高解約返戻率の法人保険(節税目的のみ)
- 契約形態:短期間で解約返戻率が高くなるタイプ
- 損金算入:2019年改正で制限
- 問題点:税務調査で否認される可能性が高く、逆に多額の追徴課税リスク。
実務での保険活用のポイント
1. 契約目的を明確化
契約書や稟議書で「事業保障目的」であることを明記すると、税務上の説明がしやすくなります。
2. 解約返戻率を確認
高解約返戻率タイプは節税効果が制限されているため、契約前に返戻率表を確認します。
3. 福利厚生型かどうか
従業員全体を対象にした福利厚生型保険は、損金算入の可能性が高くなります。
4. 税制改正情報を常にチェック
法人保険の損金ルールは頻繁に改正されるため、契約前に税理士へ確認することが必須です。
失敗を避けるための行動ステップ
- 現状の保険契約の棚卸し
- 契約者、被保険者、保険金受取人、解約返戻率を一覧化。
- 損金算入可否の判定
- 税務ルールに照らして分類(損金可・不可・一部可)。
- 必要のない保険の見直し
- 節税効果がなく資金拘束だけしている契約は解約や減額を検討。
- 新規契約は専門家と相談
- 税理士や保険コンサルと協議し、税務面・保障面・資金繰り面を総合判断。
- 将来の解約時課税もシミュレーション
- 節税は契約時だけでなく、解約時の課税も含めてトータルで判断。
まとめ
- 節税になる保険は、事業関連性が高く、貯蓄性が低いものが中心。
- 貯蓄性の高い保険は資産計上となり、節税効果は限定的。
- 税制改正や税務調査のリスクを考慮し、専門家とともに契約判断を行うことが重要。
- 「節税目的だけ」の契約は将来の負担増につながる可能性があるため注意。