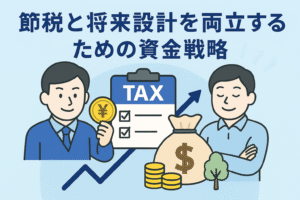社長の給与、何となく決めていませんか?
中小企業の社長や経営者の方にとって、自分の給与(役員報酬)をいくらに設定するかは、節税にもキャッシュフローにも直結する重要な判断です。
「とりあえず前年と同じ金額で」
「儲かったからちょっと増やしてみるか」
「報酬は少なめにして会社に残そう」
こういった“なんとなく”の報酬設定では、税負担が増えたり、資金繰りが悪化したりするおそれがあります。特に2025年現在、法人税・所得税・住民税・社会保険料といった多層的な課税をトータルで見ないと「損な設計」になってしまうことも。
この記事では、社長の給与を戦略的に設計し、所得分散を活用して節税する方法を詳しく解説します。
報酬の決め方を間違えると「税金で損をする」?
「社長の給与」と一言でいっても、単に「いくら欲しいか」で決めるものではありません。実際には次のようなさまざまな税金やコストが絡みます。
- 法人税とのバランス(会社が支払う税金)
- 所得税・住民税(社長個人が支払う税金)
- 社会保険料(会社負担+個人負担)
例えば、以下のような設定だとどうなるでしょうか。
| 役員報酬(月額) | 年間役員報酬 | 所得税・住民税 | 社会保険料 | 法人の利益(概算) | 法人税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 1,200万円 | 高い(累進税率) | 約300万円以上 | 小さくなる | 少ない |
| 50万円 | 600万円 | 中程度 | 約150万円 | 大きくなる | 多い |
→ 報酬を高くしすぎても、法人・個人トータルで税金や保険料が増える可能性があります。
最適な報酬設計+所得分散が節税のカギ
社長の給与設計は「法人と個人のバランスを見て、全体として支払う税金・社会保険料を抑える」ことが基本です。
さらに節税効果を高めたいなら、「所得分散」の考え方が効果的です。
所得分散とは?
所得を1人で集中して得るのではなく、家族や親族など複数の人に分散させることで、全体の税負担を抑える手法です。
- 所得税は累進課税(所得が多い人ほど税率が高い)
- 分散することでそれぞれの税率が下がり、トータルの納税額が減少
所得分散の主な手法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 家族を役員にして報酬を払う | 配偶者や子を役員に登用し、合理的な報酬を支給 |
| 家族に給与を払う | 経理や総務などの実務に関与してもらう |
| 家族名義で副業収入を得る | 資産管理会社や不動産収入などで名義分散 |
このような所得分散は、法人・個人の両方にメリットをもたらす「合法的な節税手段」です。
なぜ高額報酬は損になる?税制・社会保険料の仕組み
税制と社会保険の基本構造を理解する
所得分散による節税を正しく理解するためには、まず個人課税(所得税・住民税)と法人課税(法人税)、そして社会保険料の構造を押さえておく必要があります。
所得税と住民税は「累進課税」
所得税の基本は「稼げば稼ぐほど税率が上がる」累進課税制度です。
所得税の税率(2025年現在)
| 課税所得(年額) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~195万円 | 5% | 0円 |
| ~330万円 | 10% | 97,500円 |
| ~695万円 | 20% | 427,500円 |
| ~900万円 | 23% | 636,000円 |
| ~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| ~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※上記に加えて、一律10%の住民税が課税されます。
例:年収1,200万円の場合
- 所得税:約185万円前後
- 住民税:約120万円前後
- 合計:約300万円超の税負担
→ 税率が30%を超えるため、「1人で高額所得」を取るほど税負担が重くなるのがわかります。
法人税は定率課税(比較的フラット)
一方、法人にかかる法人税等(法人住民税・事業税などを含む)は、利益に対して一律約30%前後が基本(所得800万円以下は軽減税率あり)。
法人税のメリット
- 所得税と比べて高額になっても急激には上がらない
- 経費計上できる範囲が広い(福利厚生費・交際費など)
- 将来の内部留保や投資にまわせる
→ 会社に利益を残した方が、個人で高い税率を取られるより効率が良いことが多いのです。
社会保険料は報酬に連動して増える
役員報酬が高くなると、連動して**社会保険料(健康保険・厚生年金など)**も増加します。
社会保険料の仕組み
- 報酬月額が高いほど保険料率が上がる
- 個人負担と法人負担が「半分ずつ」
- 上限はあるが、年収1,000万円超で年間約300万円前後の負担も
高額報酬の弊害:個人も法人もダブルで損?
| 報酬が高すぎると… | 結果 |
|---|---|
| 所得税・住民税が累進で高負担 | 税金だけで年収の30〜45%が消える |
| 社会保険料も増える | 年間100〜300万円以上の追加コスト |
| 法人側の費用が増加(社会保険料) | 法人に利益が残らず、設備投資・留保が困難に |
| 節税策が限られる | 経費化できずに個人資産として課税リスク大 |
所得分散の効果とは?
このような税金と社会保険料の“複合的な負担”を軽減するために有効なのが、所得分散です。
- 家族や親族への報酬や給与の支払いにより、個人課税を「分散」
- 社長1人で受ける高税率ゾーンを避ける
- 法人側での経費化もできるため、法人税も減らせる
- 社会保険料も抑えられる可能性あり(適用範囲に注意)
社長・配偶者・子どもに分散する実例と注意点
所得分散は、合法的に税負担を軽減できる有効な手段です。しかし、「どのように分散するか」「税務署に否認されないために何が必要か」など、慎重に設計することが求められます。
以下に、代表的な3つのケースを紹介します。
ケース①:配偶者を役員に登用して報酬を支払う
【背景】
社長が年収1,000万円、妻(専業主婦)に経理や事務作業を任せて役員報酬を設定。
【設計】
| 項目 | 社長単独(分散なし) | 所得分散後 |
|---|---|---|
| 社長報酬 | 1,000万円 | 700万円 |
| 配偶者報酬 | 0円 | 300万円 |
| 合計税金負担 | 約290万円 | 約200万円前後(夫婦合計) |
【ポイント】
- 業務内容が実在し、報酬水準が合理的であることが前提
- 取締役就任は登記が必要。議事録や報酬規定も整備すべし
- 配偶者の社会保険の加入有無にも注意(130万円の壁など)
ケース②:子どもにアルバイト報酬を支払う
【背景】
高校生や大学生の子どもに、ホームページ作成や商品撮影など業務を依頼。
【設計】
| 項目 | 分散なし(社長のみ) | 分散あり |
|---|---|---|
| 社長報酬 | 1,200万円 | 1,000万円 |
| 子ども報酬 | 0円 | 200万円 |
| 合計税負担 | 高税率ゾーン突入 | 全体で減税可能 |
【ポイント】
- 業務実態と支払い内容(時給や成果物)を明確にすること
- 子の年収が一定額以下なら所得税・住民税がかからない場合も
- 家族の扶養関係とのバランスに要注意
ケース③:実務従事の家族に給与を支払う(青色事業専従者)
【背景】
個人事業主のケース。青色申告者が家族を従業員として登録し、給与を支給。
【注意点】
- 「青色事業専従者給与」の届出書を提出することが条件(事前申請)
- 生計を一にする15歳以上の家族が対象
- 所得分散効果あり+給与は必要経費に算入可能
所得分散の注意点と落とし穴
税務署に否認されるリスク
- 実態がない“名ばかり役員”や“形式的な給与”は否認される可能性あり
- 適正な報酬額、業務内容の証明(勤怠記録、成果物、業務日報など)が必要
税制改正の影響
- 過去には「配偶者控除の廃止・縮小」や「給与所得控除の見直し」が行われており、今後も制度変更に注意が必要
社会保険への影響
- 家族が社会保険に加入することで保険料負担が増える可能性
- 配偶者控除・扶養の条件も影響するため、手取りベースで損得を判断する必要あり
報酬設計の手順と所得分散の実践ステップ
高額な税金・社会保険料に悩まされず、かつ税務的にも安全な範囲で節税を行うには、「計画的な報酬設計」と「戦略的な所得分散」がカギとなります。
ここでは、節税を意識した報酬設定と所得分散のために押さえるべき実践ステップを紹介します。
ステップ1:現在の法人利益と報酬水準を把握する
まずは自社の経営状況を正確に把握しましょう。
- 直近1〜2年の法人税額、役員報酬額、利益の推移
- 経営計画(売上・利益の見込み)
- 社会保険料の負担状況(法人・個人とも)
ポイント
- 法人利益が多すぎる → 報酬を増やす余地がある
- 社長の所得税・住民税が高すぎる → 報酬を減らす or 分散を検討
ステップ2:年間の納税額シミュレーションを行う
法人と個人の税金・社会保険料をトータルで比較し、最も手取りが残るバランスを見つけることが重要です。
比較シミュレーションで見るべき項目
- 法人税(利益に対する課税)
- 所得税・住民税(報酬に対する課税)
- 社会保険料(報酬に応じた負担)
- 経費にできる支出の範囲
税理士に依頼して「報酬変更パターン別の実効税率・手取り額」を試算してもらうのがおすすめです。
ステップ3:家族への給与・報酬支払いの体制を整える
所得分散を実施するには、実態と証拠がセットで必要です。
実務上の準備
- 家族に明確な業務を割り当てる(経理補助・Web管理・事務など)
- 労務管理の体制整備(勤怠管理・契約書・報酬明細)
- 取締役登記(役員とする場合)
- 税務署への届出(青色事業専従者など)
ステップ4:報酬設計の変更は期首に行う
法人の役員報酬は、原則として「期首から3ヶ月以内」に決定しなければなりません(定期同額給与の要件)。
※途中で変更すると、損金不算入になるリスクがあります。
必要な書類例
- 株主総会議事録または取締役会議事録
- 役員報酬規程・就任契約書
- 登記簿(役員追加の場合)
ステップ5:定期的な見直しを習慣化する
制度は変わります。経営状況も変わります。だからこそ、毎年の決算時期に合わせて「報酬と税金の最適化」をルーチンにしましょう。
- 売上や利益の増減に応じて報酬水準を調整
- 所得税・社会保険料の増加に注意
- 制度変更(控除・課税対象の見直し)に対応
よくあるQ&A
Q. 子どもに報酬を払うのは脱税になりますか?
→ 実際に業務に従事しており、報酬額が妥当であれば問題ありません。ただし「名義貸し」は違法なので注意。
Q. 家族を役員にしても節税になるとは限らないのでは?
→ 給与をもらう側の課税状況や、社会保険の加入義務によっては手取りが減るケースもあります。必ずシミュレーションを行ってください。
Q. どんな保険や制度と組み合わせるとさらに節税できますか?
→ 以下との併用がおすすめです:
- 小規模企業共済(役員退職金の積立)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 法人向け生命保険(損金算入型)
- 倒産防止共済(取引先リスク対策+節税)
報酬と所得を“戦略的に設計”することが節税の鍵
社長の給与設定は、法人と個人の両面にまたがる重要な財務判断です。ただ金額を決めるだけでなく、「税負担・社会保険・キャッシュフロー」のバランスを見ながら戦略的に設計する必要があります。
そのうえで、所得分散は非常に有効な選択肢のひとつ。
制度を理解し、実務的な準備と税務的根拠をしっかり整えることで、合法的な節税と家族への資産移転の両立が可能になります。