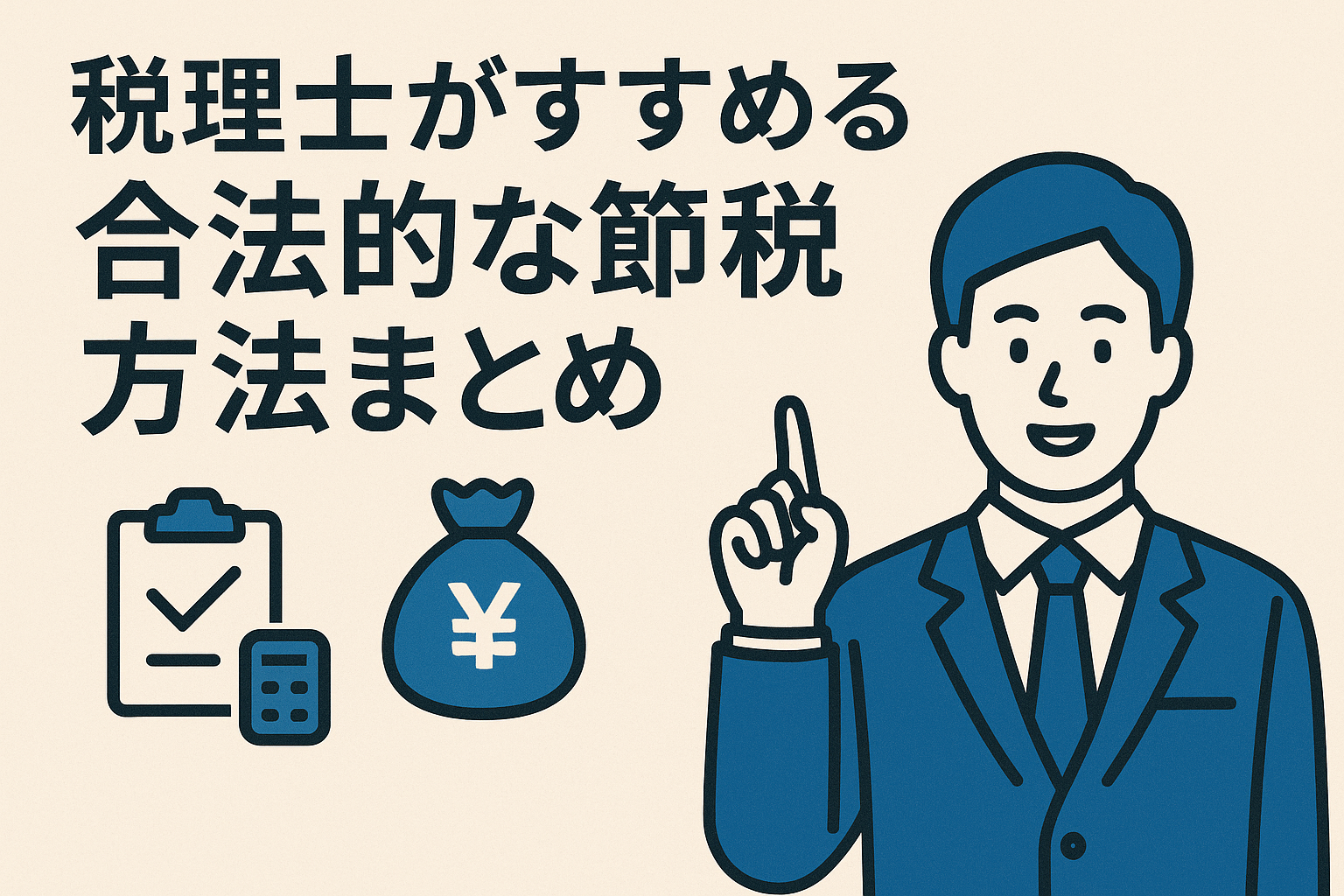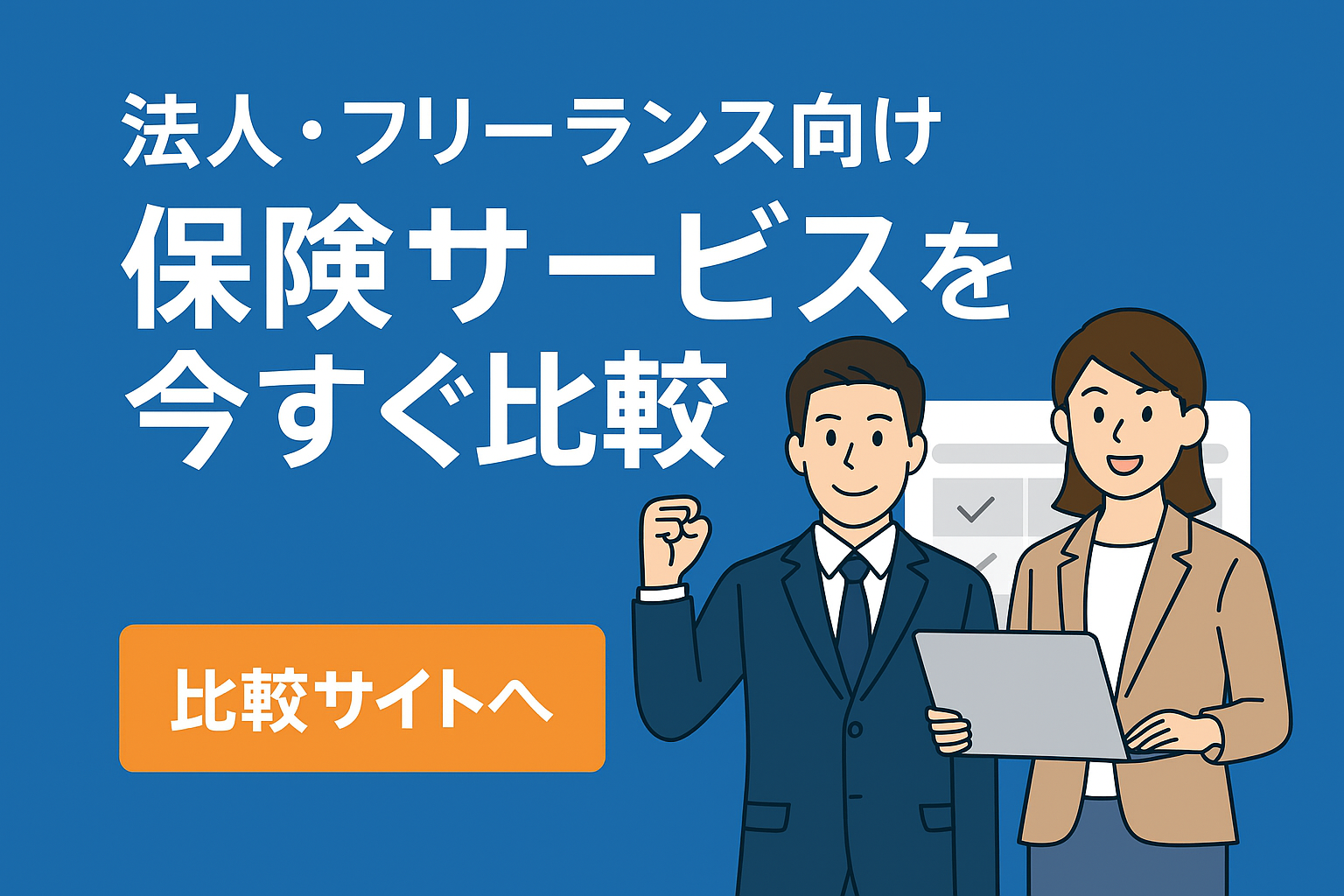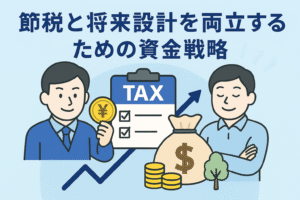節税は“賢く経営する人”が必ずやっている
「もっと利益を上げたい」「なるべく税金は減らしたい」
これは、すべての個人事業主・中小企業経営者にとって共通の願いです。
しかし、「節税=脱税すれすれのグレーな手段」と誤解されることも少なくありません。実際には、税理士が提案する節税の多くは、**合法的であり、かつ制度に基づいた“賢い選択”**です。
本記事では、**「税理士が安心しておすすめできる合法的な節税方法」**を、体系的にわかりやすく解説します。
「なぜその方法が節税になるのか」「どんな人に向いているのか」まで含め、今日から実践できる節税の基本と応用を紹介していきます。
「税金が高すぎる…」と思ったら読むべき理由
多くの事業主が、次のような悩みを抱えています。
- せっかく利益が出ても税金で大半が消える
- 頑張って稼ぐほど課税所得が増えていく
- 決算前になってから慌てて経費を増やそうとする
- 顧問税理士が節税提案してくれない
- そもそも「何をすれば節税になるのか」が分からない
これらの悩みは、実は**「知識があるかどうか」だけで解決できることも多い**のです。
節税の基本は「制度を活かすこと」
節税は「裏技」ではありません。
国が定めた制度やルールを理解し、正しく使うことが節税の本質です。
制度を知らなければ、必要以上に税金を払ってしまう一方で、制度を知っているだけで何十万円、場合によっては数百万円の節税が可能になります。
節税に失敗する人の特徴とは?
以下のような行動パターンの人は、節税チャンスを逃してしまいがちです。
| タイプ | 具体例 | リスク |
|---|---|---|
| ① 後回し型 | 決算ギリギリで節税策を考える | 対策が間に合わない |
| ② 無関心型 | 節税は面倒だからと無視 | 税額が膨らむ |
| ③ 任せすぎ型 | 税理士に丸投げ | 自社に合った提案が得られないことも |
| ④ グレー志向型 | 何でも経費にしたがる | 税務調査で否認される危険 |
正しい節税は「3つの視点」で考える
本記事では、以下の3つの視点から節税を分類し、具体策を提案します。
🔹 ① 支出型節税
…経費計上できる支出を工夫することで、課税所得を抑える方法
🔹 ② 制度活用型節税
…国の制度(共済・税額控除・特例など)を活用して税額を直接減らす方法
🔹 ③ 資産形成型節税
…保険や退職金などを通じて、将来の備えと節税を両立させる方法
① 支出型節税:経費の使い方で合法的に税負担を軽減する
「どうせ払うお金なら、節税に効く支出に変える」
それが支出型節税の基本的な考え方です。
🔸 節税しながら将来にも役立つ支出とは?
| 節税方法 | 内容 | 節税メリット |
|---|---|---|
| 備品・消耗品の年内購入 | PC・ソフトウェア・消耗品など | 全額経費にできる(10万円未満) |
| 青色事業専従者給与 | 家族に仕事を手伝ってもらい、給与を支払う | 事業所得から控除可(要届出) |
| 広告宣伝費 | SNS広告・チラシ・HP制作費など | 全額経費、ブランディングにも貢献 |
| 会議費・交際費 | 打ち合わせ・懇親会など | 飲食費は1人5,000円以下で認められやすい |
| 賃貸オフィス・自宅兼事務所の家賃按分 | 自宅の一部を事務所として経費化 | 家賃や光熱費の一部を計上可 |
💡 青色事業専従者給与の注意点
- 届け出が必要(税務署に)
- 実際に業務を行っていることが前提
- 金額が相場から大きく乖離していると否認リスクあり
🔍 支出型節税の効果的なタイミングとは?
- 決算月の前月〜2ヶ月前がベスト
- 支出だけでなく納品・使用開始が完了していることが原則
- 期末の駆け込み購入は注意(資産計上になる場合も)
② 制度活用型節税:国の制度を活かして税金を減らす
次に、“使える制度を使うだけ”で節税になる方法を紹介します。
🔸 小規模企業共済
| 内容 | 事業主の退職金を自分で積み立てる制度 |
|---|---|
| 掛金 | 月1,000円〜7万円(全額所得控除) |
| メリット | ① 所得税・住民税の節税 ② 退職・廃業時の資金確保 |
| 注意点 | 中途解約は元本割れの可能性あり |
✅ 年間最大84万円の所得控除!
→ 年収500万円なら約16万円の節税効果も。
🔸 iDeCo(個人型確定拠出年金)
| 内容 | 自分で積み立てて老後に備える年金制度 |
|---|---|
| 掛金 | 月5,000円〜68,000円(自営業者の場合) |
| メリット | ① 掛金全額が所得控除 ② 運用益も非課税 ③ 老後の資産形成に |
| 注意点 | 原則60歳まで引き出せない(資金拘束) |
🔸 セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
| 内容 | 取引先倒産時の資金確保に備える制度 |
|---|---|
| 掛金 | 月5,000円〜20万円(年240万円上限) |
| メリット | ① 全額損金処理できる ② 節税と資金繰りの両立 |
| 注意点 | 12ヶ月以上の加入で貸付利用可/解約時は課税対象になることも |
✅ 制度活用型節税は「長期的な視点」がカギ
| 制度名 | 節税効果 | 資金の自由度 | 将来の備え |
|---|---|---|---|
| 小規模共済 | ◎ | △ | ◎ |
| iDeCo | ◎ | ✕ | ◎ |
| セーフティ共済 | ◎ | ○(貸付制度あり) | ○ |
ポイント:節税は「支出」と「制度」の組み合わせで最大化できる
実際には、たとえば以下のような組み合わせ戦略が効果的です。
📘 例:利益800万円の法人が節税を目指すケース
| 節税施策 | 節税効果 |
|---|---|
| セーフティ共済 年240万円 | 全額損金処理 → 実効税率30%として約72万円の税負担減 |
| 小規模企業共済 年84万円 | 所得控除 → 約16万円節税 |
| 決算前にPC購入 20万円 | 経費処理 → 約6万円の節税効果 |
→ 合計で約94万円の節税インパクト
③ 資産形成型節税とは?
資産形成型節税とは、将来の支出(退職金・設備更新など)を見据えた支出を今のうちに行い、経費化または損金処理することで節税につなげる方法です。
単なる「その場しのぎの節税」ではなく、事業を強くする投資型節税とも言えます。
法人保険の活用:退職金準備と節税の両立
法人で加入する生命保険を活用することで、将来の退職金・事業承継資金を積み立てながら損金処理ができます。
🔸 節税効果のある法人保険の代表例
| 保険商品 | 損金算入割合 | 主な活用目的 |
|---|---|---|
| 逓増定期保険 | 一部損金(50%など) | 退職金・事業承継準備 |
| 定期保険(全損型) | 保険料全額損金 | 短期の利益圧縮 |
| 養老保険 | 一部損金/資産計上 | 福利厚生・退職金・貯蓄型 |
💡 逓増定期保険(5年後解約で退職金)
[ 保険料支払い ] → [ 損金計上:50% ]
↓
[ 数年後に解約返戻金として資金回収 ]
↓
[ 解約時の返戻金を退職金などに充当 ]
注意点
- 税制改正で「損金割合の制限」が厳しくなっており、最新の通達やルールを確認する必要あり
- 解約返戻金が大きくなるタイミングで一時的な利益計上が発生するため、トータルでの節税設計が必要
役員退職金制度の導入
将来の役員退職金を適切に設計しておくことで、法人税の圧縮と個人の老後資金の確保が両立できます。
退職金の節税効果
| 項目 | 法人側 | 個人側 |
|---|---|---|
| 支出時 | 損金処理可能(原則一括) | 所得計算不要(受取人) |
| 課税 | 法人税の対象外 | 個人は「退職所得控除」適用で軽減 |
| 節税効果 | 数百万円〜数千万円単位 | 税率を大幅に下げられる |
退職所得控除の計算例
- 勤続年数:20年
- 退職金:1,000万円
- 控除額:40万円 × 20年 =800万円
- 課税対象:1,000万円−800万円=200万円
→ そのうちさらに1/2課税となるため、実質課税額は100万円に対する所得税・住民税のみ
設備投資を活用した節税(中小企業向け)
新しい設備の導入や機器更新も、即時償却や特別償却制度の対象になる場合があり、節税につながります。
例:中小企業経営強化税制の活用
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 生産性向上に資する設備(機械、ソフトウェア等) |
| 償却方法 | 即時償却 or 特別償却(30%) |
| 上限 | 原則として青色申告事業者・一定の申請手続きが必要 |
| 効果 | 一括での経費化により、利益圧縮→法人税削減 |
節税以外の効果も大きい
- 生産効率UP(=利益増)
- IT化や自動化による人件費削減
- 金融機関からの評価向上
組み合わせ例:法人保険+退職金+設備投資
| 項目 | 節税タイミング | 節税効果 |
|---|---|---|
| 法人保険 | 加入時〜解約時 | 長期的に損金処理+資産形成 |
| 退職金準備 | 退職時(解約も併用) | 法人税削減+所得税軽減 |
| 設備投資 | 購入年度 | 即時償却で利益圧縮 |
今日からできる節税アクションプラン【保存版】
節税は知識だけでなく、実行することで初めて効果が出ます。
以下に、あなたが今日から取り組める節税アクションを整理しました。
✅ ステップ1:節税の全体像を把握する
- 支出型・制度活用型・資産形成型の3軸を理解する
- 「経費で落ちるもの」と「制度で減らせるもの」を切り分ける
✅ ステップ2:今すぐできる支出型節税
- 必要な備品・消耗品の購入を前倒しで検討
- 家族への給与支払い(青色事業専従者給与)を見直す
- 会議費・交際費・広告宣伝費を見直し、経費計上を徹底する
✅ ステップ3:制度を活用して節税を“仕組み化”する
- 小規模企業共済に加入
- iDeCoの上限額まで掛金設定(個人事業主は最大月68,000円)
- セーフティ共済を使って、売上の一部を「貯金+節税」に変換
✅ ステップ4:将来への備えと節税を両立する
- 退職金準備型の法人保険(逓増定期保険など)を検討
- 役員退職金規程を作成し、支払いルールを明文化
- 設備投資を通じた即時償却や特別償却制度を活用
よくある節税の失敗例と注意点
| パターン | 内容 | リスク |
|---|---|---|
| 無理な節税 | とにかく経費を増やす | キャッシュが減りすぎて資金繰り悪化 |
| グレーな処理 | 家事関連費を無理に経費化 | 税務調査で否認・追徴課税の恐れ |
| 知らない制度を放置 | 共済や控除制度の未利用 | 数十万円の損失が出る可能性も |
| 税理士任せにしすぎ | 相談せず「丸投げ」 | 自社に合った節税策が提案されにくい |
グレーとホワイトの線引きは“目的”と“証拠”
- 業務に関係がある支出か?
- 領収書・契約書など証拠書類は整っているか?
- 第三者(税務署)に説明できるか?
まとめ|節税は攻めの経営戦略
合法的な節税は、単なる税金対策ではなく、**「攻めの経営ツール」**です。
- 売上を上げるだけでなく、手元にお金を残す力がつく
- 将来の備え(退職金、設備、資産形成)と結びつけられる
- 制度を正しく活用することで、国のサポートをフルに活かせる
「節税は難しそう」と感じていた方も、本記事で紹介した手法を知ることで、“自社に合ったやり方”が必ず見えてきます。
ぜひ、できることから一つずつ取り入れて、あなたの事業を強く、安定させてください。